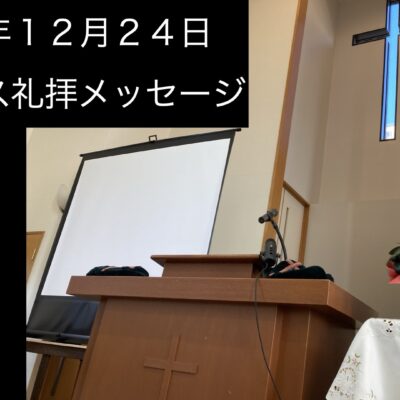聖書をお読みいたします。
聖書箇所は、ルカによる福音書14章1節〜6節。
新共同訳新約聖書136ページです。
14:1 安息日のことだった。イエスは食事のためにファリサイ派のある議員の家にお入りになったが、人々はイエスの様子をうかがっていた。
14:2 そのとき、イエスの前に水腫を患っている人がいた。
14:3 そこで、イエスは律法の専門家たちやファリサイ派の人々に言われた。「安息日に病気を治すことは律法で許されているか、いないか。」
14:4 彼らは黙っていた。すると、イエスは病人の手を取り、病気をいやしてお帰しになった。
14:5 そして、言われた。「あなたたちの中に、自分の息子か牛が井戸に落ちたら、安息日だからといって、すぐに引き上げてやらない者がいるだろうか。」
14:6 彼らは、これに対して答えることができなかった。
「もし、自分の子だったら」と題して、村田悦牧師に、メッセージをしていただきます。
・子どもメッセージ
今日の箇所には、イエス様が、病気の人を癒やされた話が記されています。
聖書には、そういう話が、たくさん書かれていますが、今日の話は、ちょっと特殊で、その日は、安息日だったって書かれています。
安息日って、なんの日か、知っていますか。
漢字で書くと、安心して息をする日って書きます。
安心して息をする日、そう、それは、お休みの日のことです。
安息日っていうのは、お休みの日なんですが、単なる休みの日じゃない。
神様が定められた休みの日。
1週間に1日、神様が定められた休みの日。
それが安息日です。
その日には、いかなる仕事もしてはならないって、聖書に書いてあります。
いかなる仕事もしてはならない。
ここでいう仕事って、どんなことでしょうか。
具体的にしてはならない仕事っていうのは、39個あったと言われています。
その39を、書き出してみました。
全部見ている時間はありませんけれども、たとえば、「種を蒔く」とか「刈るとる」とか、「文字を書く」、「火をつける」というのもあります。
でも、これで終わりではありません。
この禁止事項に、さらに細かい説明があって、それが、時間が経つにつれて、どんどん増えていったそうです。
例えば、火をつけることが禁止されていますが、電気をつける時に火花が出ます。
これも、禁止事項に含まれるって考えて、安息日になったら、電気のスイッチつけてはいけないっていう人もいるそうです。
電話にも出られません。
エレベーターのスイッチも押せません。
車も、エンジンをつけると火花が出ますので、運転もしない。
火を使ってはいけないということで、料理もしない。
そんなふうに、今も、してはいけないことが増えているそうです。
そうやって、安息日には、してはならないことがたくさんあったわけですが、実は、イエス様の時代には、病人を癒すっていうのも、してはならないことだと考えられていました。
だから、イエス様が病人を癒やされた時、そこにいた人たち、みんなが、その様子を見ていたそうです。
どんな眼差しで、見つめていたか。
きっと「あ!あいつ、してはいけないことをした!」心の中で、そんなことを思いながら、見つめていたんだと思います。
そんな人たちに、イエス様は、言いました。
「もし、この病人が、あなた方の子どもだったら、どうしたか。
安息日だって関係なく、すぐに助けるだろ。」そうイエス様は言われたんです。
言われた人たちは、どう思ったでしょうか。
きっと、病人を見つめる目が、変わったと思います。
もし、この人が、自分の子どもだったら、自分はどうしていただろうか。
安息日のことばっかり考えて、目の前の人のことを全然考えていなかった。
そのことに気づかされて、心が、揺れ動かされていただろうと思います。
もしかすると、イエス様は、いつも、目の前の人を、自分の子どもだって思いながら、接していたのかもしれません。
だからこそ、出会う一人一人を、大切に、愛を込めて、接することができたのかもしれない。
そして、きっとイエス様は、私たち一人ひとりも、自分の子どもって思って、今も、愛を注ぎ続けてくださっているのだと思います。
そのことを信じて、今日から始まる新しい1週間、私たちも、このことにチャレンジしてみたいと思います。
出会う一人一人を、自分の大切な人だって、思いながら接してみる。
お父さんでも、お母さんでもいい。兄弟でもいい。親友でもいい。
出会う人一人一人を、自分の大切な人だって、思いながら接してみる。
そしたら、どうなるでしょうか。どんなことが起こるでしょうか。
イエス様の言葉に導かれて、新しい1週間を、始めていきましょう。
お祈りします。
・安息日は何の日か
今日の箇所には、イエス様が、安息日に、食事をするために、ファリサイ派の議員の家にお入りになった時のことが記されています。
先ほど安息日は、神様が定められた休日だと言いましたが、より厳密にいうと、その日は、神様が、天地万物を完成され、7日目に休まれたこと、安息されたことを記念する日です。
単なる休日ではない。
天地創造の神の業を感謝し、互いにつくられたものとして、尊び合う日。
それが、安息日です。
ですから、ユダヤ人は、安息日になると、家族や大事な人たちで集まって食事をし、そして、神様を礼拝するそうです。
いかなる仕事もしてはならないというのは、そのための手段であって、目的ではありません。
ファリサイ派の人々は、そのことを、見失っていたのではないでしょうか。
律法を守るということで頭がいっぱいで、目の前の人のことが見えなくなっていた。
イエス様の言葉を中心に、今日の箇所を読んでいく時、そのようなファリサイ派の人々の姿が、見えてきます。
このことを念頭におきながら、今一度、今日の箇所を読んでいきたいと思います。
・なぜ、水腫の人がいたのか
1節、安息日のことだった。イエスは食事のためにファリサイ派のある議員の家にお入りになったが、人々はイエスの様子をうかがっていた。
ファリサイ派というのは、ユダヤ教の一派で、律法に厳格な人たちでした。
当然、安息日の律法も厳格に守って、この日も過ごしていたのだと思います。
そんなファリサイ派の人々と食事をするために、イエス様は、彼らの家に入っていきました。
するとそこに、水腫を患っている人がいました。
私は、ここに、すごい違和感を感じました。
なんで、ファリサイ派の家に、水腫の人がいたんだろうか。
水腫とは、体に、余分な体液が溜まる病気です。
皮下組織に溜まると浮腫(むくみ)、体の中に溜まると胸水や腹水などと呼ばれます。
この病気は、当時、罪の報いだと考えられていました。
つまり、水腫の人は、罪人だと思われていたということです。
ファリサイ派の人々は、そのような人々と食事をすることを、極端に避けていました。
イエス様が、罪人と共に食事をしている時、「なぜあなた方は、罪人などと一緒に、飲んだり食べたりしているのか」と、そうつぶやく場面も、福音書の中に記されています。
それほど、ファリサイ派の人々は、罪人と関わること、まして、食事をすることなど、ありえないことだと思っていたわけです。
それなのに、なぜ、今日の場面では、ファリサイ派の人々の家に、水腫の人がいたのでしょうか。
一緒に食事をするためだとは、どうしても、思えない。
実際、彼は、食事をすることなく、家に帰っています。
食事をするためでないとすると、一体何のために、彼は、この場に、招かれていたのでしょうか。
・イエス様を試すため
そのことを考える時、1節の最後に記されています、「人々はイエスの様子をうかがっていた。」という言葉がひっかかりました。
家に入る時から、人々は、イエス様の動向を気にしていました。
なぜ、気にしていたのか。
それは、水腫の人と出会うのがわかっていたからではないでしょうか。
水腫の人に対して、イエスは、どうするか。
安息日に禁止されている癒しを行うかどうか。
そのことを気にして、人々は、イエスの様子を伺っていたのではないでしょうか。
と考えると、水腫の人が何のために、ファリサイ派の家にいたのかが、見えてきます。
それは、イエス様を試すためです。
イエス様が、安息日にどう行動するか。
安息日規定を守るかどうか。
そのことを試すため、あるいは、守らなかった場合、これを口実に、イエス様を訴えようと、そう考えていたかもしれません。
ルカによる福音書を、続けて読んできた方は、お分かりだと思いますが、これまでの箇所には、イエス様とファリサイ派の衝突が何度も語られていました。
律法に厳格なファリサイ派に対して、イエス様は、隣人を愛することを、律法の最も重要な掟として考え、行動していました。
時に、その行動は、ファリサイ派の人々の目に余るものでした。
今日の箇所に記されているような、安息日規定を度外視して、病人を癒す場面も、実は、今日の箇所で5箇所目になります。
その度に、ファリサイ派の人々は、怒りを募らせ、激しい敵意を抱き、どうしたらイエスを懲らしめることができるか、おとなしくさせることができるか、考えていたと記されています。
もしかすると、今日の箇所は、その企みを実行に移した日だったのかもしれません。
イエス様を訴えるために、日頃、かかわりを避けていた水腫の人を家に招いていた。
つまり、水腫の人は、イエス様を罠にかけるために使われたということです。
・なぜそんなことができたのか
なぜ、そんなことができたのでしょうか。
そのことを考える時に、イエス様の言葉が、心に響きます。
5節「あなたたちの中に、自分の息子か牛が井戸に落ちたら、安息日だからといって、すぐに引き上げてやらない者がいるだろうか。」
私は最初この言葉を読んだ時、自分の息子と牛が同等に語られているというのが、なんとも違和感があったのですが、それは、家畜差別でしょうか。
そうかもしれませんが、きっと言いたかったことは、こういうことだと思います。
「もし自分の息子が、井戸に落ちたとしたら、安息日だからと言って、引き上げてやらない者がいるだろうか。
たとえ落ちたのが家畜だったとしても、すぐに引き上げてやるだろう。」
自分の息子なら尚更、家畜であったとしても、すぐに引き上げるだろう。
それが、この言葉の趣旨だと思います。
ここで大事なのは、イエス様が、自分の息子に置き換えて、考えたということです。
「助けを求めているのが、自分の息子だったら…」
この想像力、この視点が、非常に大切であると、教えられます。
「もし、自分の息子だったら…」というイエス様の問いかけは、水腫の人との距離感を、ぐっと近づける言葉だったと思います。
距離感というのは、関係の距離感です。
それまで、ファリサイ派の人々は、水腫の人を、自分たちとは関係のない、別世界の人間だと思っていた。
繋がりがない。関係が切れている。
だから、都合の良い道具のように、扱うことができたんだろうと思います。
子どもメッセージでも言いましたが、イエス様の言葉を聞いた人々は、きっと、水腫の人を見つめる目が、変わったと思います。
もし、この人が、自分の子どもだったら、自分はどうしていただろうか。
安息日のことばかり考えて、目の前のこの人のことを全然見ていなかった。
そのことに気づかされて、心が、揺れ動かされていたことだろうと思います。
・無縁社会による人のモノ化
このファリサイ派の人々の課題というのは、私たちと、決して無関係ではない。
むしろ、彼らの課題は、私たちの生きる社会の課題であり、私たち自身の課題でもあるように感じます。
2008年のリーマンショック以降、雇い止めや派遣切りという言葉が、広まりました。
派遣労働者を使い捨てにしている問題が、社会問題として、注目されるようになりました。
それから、15年が経過した今、この課題は、在日外国人の雇用問題につながっています。
2022年の厚生労働省の調査によると、外国人労働者の人数は、過去最高の182万人。
中でも、最も多いのが、技能実習生で、34万人だそうです。
この技能実習制度は、開発途上国への技能移転、開発途上国の経済発展を担う「人づくり」に協力するということを目的で作られました。
安価な労働力を得るための手段として、使われてはいけないと、法律で定められています。
しかし、残念ながらそれは建前で、実態は、低賃金によって、過酷な労働を強いられているというのが現状です。
これは、以前から問題になっていたことですが、厳しい職場環境に置かれた実習生の失踪が相次いで起こったり、人権侵害の指摘、勧告が増える中、昨年末、政府の有識者会議は、今の制度を廃止するとした最終報告をまとめ、新たな制度に移行していくと、発表しました。
私たちの教会にも、時々、技能実習生の方が来てくださいます。
中には、ほとんど日本語を話せない方もいらっしゃいます。
昨年まで、来てくださっていた方も、日本語は、ほとんど話せませんでした。
それでも、交わりを求めて教会に来てくださっていました。
英語も話すことが難しかったので、話す時には、いつも、携帯の翻訳機を使っていました。
ある時、その方から、ビザが切れるので、日本語試験の勉強がしたいと、言われました。
その方は、技能実習1号の方で、在留期間が1年しかなかったので、技能実習2号を取得して、ビザを更新したいということでした。
でも、そのためには、日本語の試験をクリアーしなきゃいけない。
でも、日本語学校に行くお金はないということで、私に相談してきたわけです。
その方は、英語も難しかったので、その方の母国語で日本語を教えてくれる人を探しました。
探したところ、その方の母国語で、日本語を教えてくれるという方を紹介してくださる方と出会うことができました。
ま、最終的には、勉強する時間がなかったり、体調を崩したりで、実施することは叶わなかったのですが、
ともかく、その方と会って、話をすることができました。
その時に、技能実習生の方が、「試験に合格したら、大分で働きたい。何か良い仕事ありませんか。」とその方に聞きました。
すると、「仕事を選んじゃダメ。外国人は、日本人がやりたがらないことをしないと。それが、あなたたちの仕事です。」って、そう言われたんです。
びっくりしました。とても、技能実習生の方に、伝えることなどできませんでした。
このようなことは、今に始まったことではありません。
戦前戦中戦後と、トンネル工事や、石炭労働、大本営建設、危険で命懸けの作業を押し付けられたのは、朝鮮人労働者でした。
その構造は、今も、何も変わっていないんだと、そう思わされました。
ファリサイ派の人々の課題というのは、まさに、私たちの社会の課題であり、私たち自身の課題です。
その課題を乗り越えていくために、イエス様の言葉を心に留めたいと思います。
全ての人が、人として、尊重される社会をつくっていく。
そのためのヒントとして、相手のことを、自分の大切な人に置き換えて想像してごらんと、イエス様は招いています。
もし、この人が、自分の子どもだったら、家族だったら、友人だったら。
あるいは、自分自身だったら、どう感じるか。
今日の礼拝の、招きの言葉で、「隣人を自分のように愛しなさい」という言葉を聞きました。
それは、自分に置き換えて、考えてみなさいという招きでもあると思います。
この招きに応えていきたいと思います。
まず、私たち一人ひとりが、イエス様の子どもとして、愛され、受け入れられている。
そのことを信じながら、私たちも、相手のことを、自分の大切な人として、自分自身として、尊重できるものとなっていきたい。
そのように願います。
お祈りいたします。