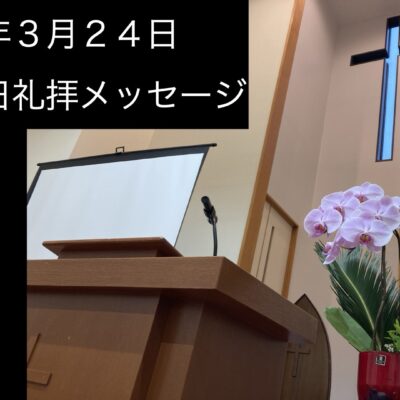聖書
聖書をお読みいたします。
聖書箇所は、ルカによる福音書6章43節〜49節。
新共同訳新約聖書114頁です。
7:1 イエスは、民衆にこれらの言葉をすべて話し終えてから、カファルナウムに入られた。
7:2 ところで、ある百人隊長に重んじられている部下が、病気で死にかかっていた。
7:3 イエスのことを聞いた百人隊長は、ユダヤ人の長老たちを使いにやって、部下を助けに来てくださるように頼んだ。
7:4 長老たちはイエスのもとに来て、熱心に願った。「あの方は、そうしていただくのにふさわしい人です。
7:5 わたしたちユダヤ人を愛して、自ら会堂を建ててくれたのです。」
7:6 そこで、イエスは一緒に出かけられた。ところが、その家からほど遠からぬ所まで来たとき、百人隊長は友達を使いにやって言わせた。「主よ、御足労には及び ません。わたしはあなたを自分の屋根の下にお迎えできるような者ではありません。
7:7 ですから、わたしの方からお伺いするのさえふさわしくないと思いました。ひと言おっしゃってください。そして、わたしの僕をいやしてください。
7:8 わたしも権威の下に置かれている者ですが、わたしの下には兵隊がおり、一人に『行け』と言えば行きますし、他の一人に『来い』と言えば来ます。また部下に 『これをしろ』と言えば、そのとおりにします。」
7:9 イエスはこれを聞いて感心し、従っていた群衆の方を振り向いて言われた。「言っておくが、イスラエルの中でさえ、わたしはこれほどの信仰を見たことがない。」
7:10 使いに行った人たちが家に帰ってみると、その部下は元気になっていた。
「小さき者のために権威を使われるイエス様」と題して、村田悦牧師に、メッセージをしていただきます。
子どもメッセージ
今日は、みんなに一つ質問があります。
もし、みんなが、一つだけ、願いを叶えることができるとしたら、どんな願いにするでしょうか。
「メイクアウィッシュ」という団体があります。
その団体は、3歳から17歳までの、難病と闘っている子どもたち。
「難病」というのは、今の医学では治せない、治すことが難しい病気のことですけども、
そういう病気と闘っている子どもたちの、夢を叶えるお手伝いをしている団体です。
その団体のホームページを見てみますと、これまでに、いろんな願い事を叶えてきたことが書かれていました。たとえば、
「遊園地に行きたい」って、願いもありました。
「野生のイルカと泳ぎたい」って、願いもありました
「世界一大きいヘラクレスオオカブト虫に触りたい」って、願い事もありました。
そんな中で、磯村愛ちゃんっていう、小学4年生の女の子の願い事が、紹介されていました。
その子も、重い病気と闘っている女の子でしたが、
「一つだけ、夢が叶うとしたら、何をしてほしい」って言われて、愛ちゃんは、何と答えたか。
愛ちゃんが願ったこと。
それは、「アフリカの子どもたちに鉛筆をあげたい」ってことでした。
「アフリカには、貧しくて、学校に行けない子どもたちがいる」って、お父さんに聞いたことがあったそうです。
そのことを思い出して、愛ちゃんは、鉛筆を送りたいって思ったんだそうです。
愛ちゃんは、周りの人に呼びかけて、800本の鉛筆を集めました。
そしてそれを、アフリカのモザンビークって国にある、二つの小学校に届けることができました。
しばらくすると、その小学校から、DVDが、愛ちゃんのもとに送られてきました。
見てみると、そこには、鉛筆を受け取った子どもたちの喜ぶ姿がありました。
それを見て、愛ちゃんは、「嬉しい」って、泣いて喜んだそうです。
この話を聞いた時、私は、すごいなって思いました。
たった一度の願いを叶えるチャンスを、愛ちゃんは、自分のためじゃなく、アフリカの子どもたちのために使った。
それも、すごいなって思いますが、
その結果、鉛筆を受け取った子どもたちもそうだし、愛ちゃんも泣いて喜んだって。
そのことがすごいなって思いました。
愛ちゃんのように、私たちは、誰かのために、自分の力を使うことができます。
自分のためだけじゃなく、誰かのために、自分の力を使うことができる。
そして、そうすることで、一人じゃ得られない、大きな喜びを得ることができる。
たくさんの人たちと一緒に、喜ぶことができる。
これこそまさに、イエス様が教えてくださっている生き方だと思います。
誰かのために、自分の持っているものを使う時、喜びが二倍にも、三倍にも大きくなる。
今日は、そのことを覚えておきたいと思います。
お祈りします。
序
今日の話は、ざっくりといえば、癒しの物語ですが、
しかし、癒しの話は、ごくわずかしか語られていません。
中心的に語られているのは、百人隊長と、その信仰についてです。
特に、百人隊長の信仰については、イエス様が感心して、「イスラエルの中でさえ、これほどの信仰を見たことがない。」と言われるほど、すごい信仰であると、語られています。
「このような信仰を持ちなさい」って、直接言われているわけじゃありませんが、そんなメッセージを感じさせる箇所です。
そこで、今日は、この百人隊長と、その信仰に、注目したいと思います。
彼は何者で、また、その信仰とは、如何なるものだったのか。
そこから、ご一緒に、メッセージを聞き取っていきたいと思います。
百人隊長って?
では、まず、百人隊長とは何者か、ということを話したいと思います。
百人隊長というのは、読んで字の如く、百人からなる軍隊の隊長のことです。
今日の舞台であるカファルナウムには、領主ヘロデの軍隊が駐留していました。
この百人隊長は、おそらく、そのヘロデ軍の百人隊長でしょう。
その軍隊は、非ユダヤ人、すなわち異邦人によって構成されていましたので、この百人隊長も異邦人であったと思われます。
つまり、イエス様は、異邦人の信仰を褒めたということです。
しかも、「イスラエルの中でさえ、これほどの信仰を見たことがない」と言われました。
イスラエルの中には、祭司とか、律法学者のように、熱心に神様を信じ、仕えている人たちがいたわけですが、
そんなイスラエルの中でさえ、これほどの信仰、見たことがない。
イエス様は、そう言われたのです。
聞いていたユダヤ人にとっては、さぞ衝撃的な言葉だったでしょう。
たとえるなら、ノンクリスチャンの信仰を褒めて「クリスチャンの中にも、こんな信仰を持っている人、見たことがない」と言われているようなものです。
クリスチャンにとって、ノンクリスチャンは、伝えられる側、教えられる側、まだ信仰を持っていない人と、見なされがちですが、
異邦人の信仰を褒めるというのは、そんなノンクリスチャンの信仰を褒めるようなものです。
イエス様は、この言葉を、わざわざ従っていた群衆の方を振り向いて、言われました。
そこには、イエス様の弟子たちもいたでしょう。
彼らも、驚いたはずです。
まさか、イエス様が、異邦人である百人隊長の信仰を、褒めるなんて。
信仰と言えば、ユダヤ人。
中でも、祭司や律法学者。
彼らが信仰者の見本であるというのが、当時の人々の常識でした。
そんな常識や、当たり前のように持っていた物の見方を壊すような、そんな言葉だったと思います。
でも、実際こういうことは、珍しいことではないようにも思います。
子どもたちの信仰に、大人たちが、感心させられたり、教会に来るようになって間もない新来者の言葉に、大切なことを教えられたりすることは、よくあることです。
だから、偏見を持たないようにしたいと思わされます。
これは、特に、クリスチャンである私たちに言われていることだと思いますが、
新来者や、子どもたちは、いつも教えられる側、伝えられる側とは、限りません。
新来者や子どもたちによって、信仰の真髄が語られたり、福音が語られるということも、大いにあり得るということです。
そのことは、心に留めておきたいと思いますが、
ただ、今日の箇所に登場する百人隊長の場合、ただの異邦人ではなかったようです。
5節、(これは、ユダヤ人の長老の言葉ですが)「わたしたちユダヤ人を愛して、自ら会堂を建ててくれた」と言われています。
異邦人であるにもかかわらず、ユダヤ人を愛していた。
さらに、ユダヤの会堂を建てた人であった。
このことからも、ただの異邦人ではなかった。
異邦人だけれども、ユダヤの教えに対して、かなり理解があった人物であった、ということが伝わってきます。
中には、ユダヤ教に改宗した人だったのではないかと、言っている人もいるぐらい、
異邦人の中では、ユダヤ教に理解のある人物であったということです。
百人隊長の信仰って?
イエス様は、そんな百人隊長の信仰に、感心されたわけですが、それは、一体どのようなものだったのでしょうか。
今度は、百人隊長の信仰に、注目してみたいと思います。
彼の信仰は、彼の言葉に表れています。
6節~7節、
7:6 そこで、イエスは一緒に出かけられた。ところが、その家からほど遠からぬ所まで来たとき、百人隊長は友達を使いにやって言わせた。「主よ、御足労には及びません。わたしはあなたを自分の屋根の下にお迎えできるような者ではありません。
7:7 ですから、わたしの方からお伺いするのさえふさわしくないと思いました。ひと言おっしゃってください。そして、わたしの僕をいやしてください。
百人隊長はまず、ご足労には及びませんと言っています。
「わざわざ足を運んでいただくまでもない」ということです。
「わざわざ足を運んでいただかなくても、一言。
たった一言いただければ、それで十分です。
その通りになりますので。」
百人隊長は、そう言っているのです。
もし、みなさんの大切な人が、命を落としそうになっているとしたら、どうしますか。
大切な人が、目の前で苦しんでいる。
どうしたら良いのか、わからない。
そんな状況に置かれたら、まず、119番に電話します。
そして、救急車を呼ぶでしょう。
私も、そういう経験がありますが、
救急車を待っている時というのは、非常に時間が長く感じます。
「早く、救急車来て」「早く、救急隊来て」って、思います。
特に、百人隊長が置かれていた状況というのは、緊急事態でした。
大切な部下が、病気で死にかかっていた。
一刻も早く、処置しなければならない状況です。
それで、百人体調は、イエス様を連れてきてくれって頼んだのです。
一刻も早く、イエス様に来てほしいと思った。
でも彼は、途中で、想いを変えるんです。
「来てもらうまでもない。
イエス様なら、一言。たった一言で、病気を治すことができる。」そう信じたのです。
それだけ、イエス様の言葉を信じていたということです。
御言葉に対する信頼と、よく言われますが、
しかし、自分の大切な人の命がかかっている。
その状況で、イエス様の言葉に、全てを託せるかと言われたら、とてもできないことだと思います。
そういう意味では、確かに、すごい信仰であると思います。
イエス様の権威
でも、話はこれで終わりではありません。
彼の言葉には、続きがあります。
8節、ここには、百人隊長が、イエス様の言葉を信じた理由が、語られています。
7:8 わたしも権威の下に置かれている者ですが、わたしの下には兵隊がおり、一人に『行け』と言えば行きますし、他の一人に『来い』と言えば来ます。また部下に 『これをしろ』と言えば、そのとおりにします。」
百人隊長は、「自分は、権威の下に置かれている。」と言っています。
そして同時に、自分の下にも、兵隊がいると言っています。
要するに、典型的な縦社会の中に生きているということです。
縦社会というのは、あらゆるところで見られるものです。
会社でもそうですし、学校でも、
私も学生時代、野球部に入っていましたが、そんなに厳しくはなかったと思いますが、縦社会だったと思います。
教会にも縦社会があると思います。
私たち、バプテスト教会は、そういう権威主義的なあり方に反対した教派ですが、それでも、縦社会になりやすいものです。
そうやって、ありとあらゆるところに縦社会は見られるわけですが、
特に、軍隊は、明らかな縦社会です。
はっきりと階級が分かれていて、上位下達、上から下へ、命令が下されます。
百人隊長が言う通り、隊長が兵隊に「行け」と言えば行くし、「来い」と言えば来る。
百人隊長自身もそうだったのでしょう。
彼も、上官の命令には、文句を言わず、従ってきたのだと思います。
そうやって、下の者は、上の者に従う。
それが、軍隊です。
下の者にとって、上の者の命令、上の者の言葉は、絶対であるわけです。
それで、百人隊長は、イエス様の言葉もそうだと思ったのです。
百人隊長にとって、イエス様は、お会いするのもはばかられるような、上の方、権威のある方でした。
だから、「一言おっしゃってくだされば、それで十分」と思ったのです。
確かに、イエス様は、権威あるお方です。
人だけでなく、悪霊や、病気も、その言葉によって、追い出してきました。
「この人から、出て行け」と言って、悪霊を追い出したこともありましたし、
熱を叱りつけることで、高熱を去らせという場面も、ありました。
百人隊長は、きっと、そんなイエス様の話を聞いていたのでしょう。
だから、「部下を苦しめる病も、きっと、イエス様の言うとおりにするはずだ」と、信じることができたのだと思います。
でも、イエス様は、軍隊の上官なのでしょうか。
確かにイエス様は、権威あるお方で、人だけでなく、悪霊や病気も、従えるお方ですが、
そこで終わってしまったら、イエス様は、軍隊の長官になってしまいます。
それは、聖書が語っているイエス様の姿とは、違うように思います。
先週まで読んでいた、平野の説教では、むしろ、イエス様は、人々の下に立たれました。
病人や、貧しい人々、救いを求めて集まってきた人たちよりも、低みに立って、話をされました。
また、今日の礼拝の招詞で読んでいただいた箇所には、明確に「人の子は仕えられるためではなく、仕えるために来た」とおっしゃっています。
「異邦人の間では支配者たちが民を支配し、偉い人たちが権力を振るっている。
しかし、あなたがたの間では、そうであってはならない。」とおっしゃっています。
つまり、イエス様は、単に権威あるお方ではないということです。
権威あるお方だけれども、この世の権力者たちとは、違うということです。
権威を、他者のために使うイエス様
何が違うのか。
それは、権威の使い方が違うのです。
権威というのは、力であって、それ自体は、悪いものではありません。
問題は、それをどう使うかということです。
百人隊長が言うように、一般的にその権威は、自分のために使われます。
自分の都合や、自分の利益のために、行けと言ったり、来いと言ったり、そうやって使われるのが普通でしょう。
でも、イエス様は違います。
イエス様は、神様から与えられた権威。
神の子としての権威、力を、他者のために使いました。
貧しい人、病気の人、罪人のために使われました。
今日の箇所でもそうです。
イエス様は、その力を、百人隊長の部下を癒すために、使いました。
百人隊長が信じたのは、そうやって権威を用いられるイエス様です。
異邦人であり、僕であり、会ったこともない病人のために、力を用いられるイエス様です。
他者のため、貧しい人々、弱っている人々のために、その力を用いられるイエス様。
そのイエス様に対する信仰こそ、私たちが招かれている信仰なのではないでしょうか。
イエス様は、単に権威あるお方ではない。
その権威を、貧しい人々を救うため、弱っている人々を助けるために、用いられるお方だということです。
・百人隊長も、そうだった
そういう視点で見てみますと、実は、この百人隊長も、そういう人でした。
彼も、自分のためよりも、他の人のために、権威を使う人でした。
自分の権威を使ってユダヤ教の会堂を建てたり、
自分の権威を使って、死にかかっている部下のために動いたり、
そうやって、他者のために生きる人だったからこそ、みんなからも慕われていた。
その一端が、今日の箇所にも語られています。
4節~5節にある長老たちの言葉には、いやいや、やらされている感はありません。
むしろ、自らすすんで、百人隊長のためになりたい、何かしてあげたいと思っていることが伝わってきます。
そうやって、彼らは、上下関係や主従関係ではなく、互いを思いやる信頼関係、友情関係で、結ばれていたことが伝わってきます。
実際、6節には、百人隊長のために出かけて行く、友達がいたことも記されています。
部下や、僕ではなく、友達。
さらに、百人隊長は、部下を重んじる人でもありました。
岩波訳聖書では、「この僕は、その百人隊長にとって、かけがえのない者であった」と訳されています。
この百人隊長は、部下のことを、かけがえのない存在として、大切にする人であったということです。
このことから考えると、少なくともこの百人隊長は、権威的な人ではなかったということが伝わってきます。
無理やり人に命令したり、従わない者を罰したり、そういうふうに権威を使う人ではなかった。
むしろ、人のため、相手のために、自分の力を使う人だった。
そんな人だったからこそ、彼は、イエス様が、単なる権力者ではなく、
貧しい人、弱っている人々のために、権威を使われる人だと、信じることができたのだと思います。
結論
今日は、イエス様に褒められた百人隊長の信仰と、その生き様に注目しました。
その信仰は、イエス様の権威に対する信仰でした。
権威というのは、一般的に、人を服従させたり、言うことを聞かせるために用いられます。
でも、イエス様は、違いました。
イエス様は、その権威、力を、貧しい者や、弱っている者たちを助けるため、生かすために、使われました。
そんなイエス様を、信じたいと思います。
そして、同時に私たちも、イエス様や百人隊長がそうであったように、
与えられている力を、他者のために、用いられる人でありたいと思います。
そのように招かれているということを、今日は、覚えたいと思います。
お祈ります。